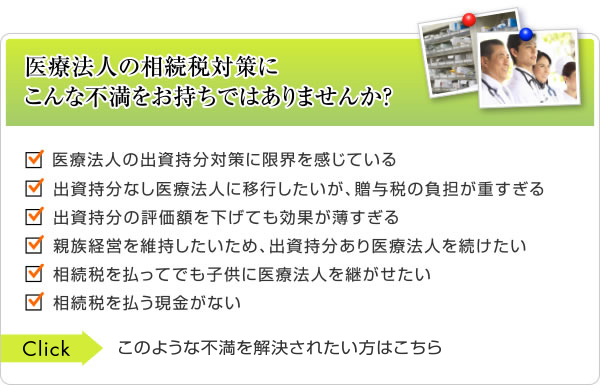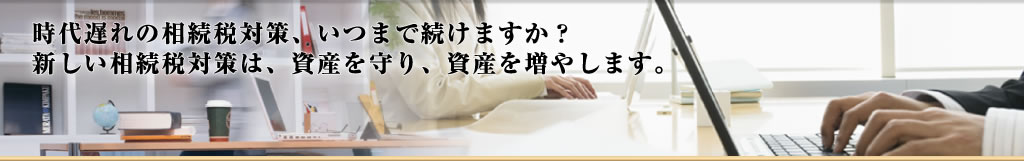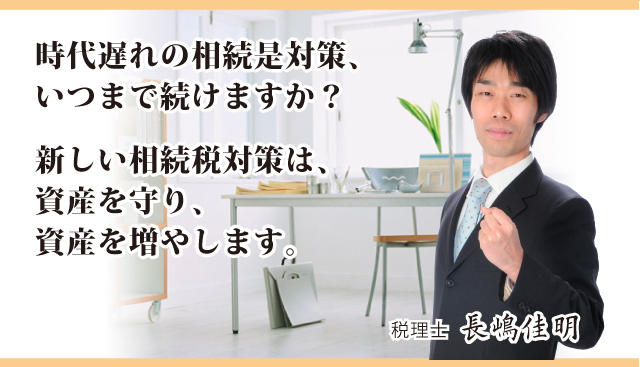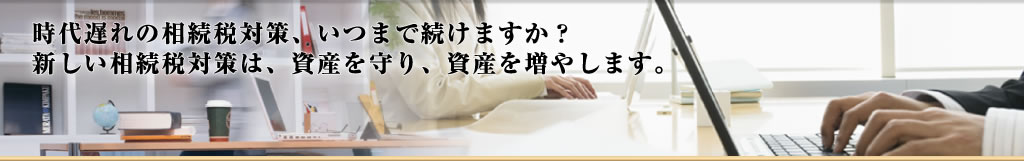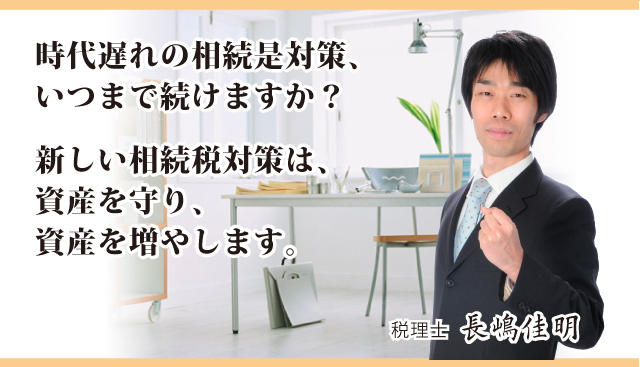先日、医療法人の理事長から相続税対策のご相談がありました。
医療法人には顧問税理士さんがおられますが、相続税対策についてアドバイスがないということで、税理士長嶋がお話を伺うことになりました。
相続税対策のお話を伺う中で、医療法人の節税についてのご相談もありました。
医療法人の節税として、保険代理店から生命保険の提案を受けているとのことでした。
この提案について、税理士長嶋の意見を求められました。
【医療法人の節税対策は、医療法に抵触する恐れあり】
医療法人の節税対策として一般的に利用されるのは「逓増定期保険」だと思います。
この保険代理店の提案も同じ内容でした。
このように、節税から提案が始まる生命保険は「医療法人に貯まった資金を無税で理事長に渡すこと」を目的としていることは明らかです。
逓増定期保険やその他の生命保険を利用した節税対策が「良いか悪いか」という以前のお話で、医療法人の存在意義そのものである「医療法」に抵触する問題となってきますのでご注意ください。
【医療法に抵触するとは?】
医療法には次のように定められています。
(1)第46条の4(利益相反取引)
医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。
この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
医療法人と理事との利益が相反する取引を行う場合、特別代理人を選任し都道府県知事の認可を受ける必要があります。
その目的が「理事長の個人的な使途のために医療法人から資金調達を行うこと」であるときは、都道府県知事は特別代理人の選任を認めません。
つまり、生命保険契約そのものができません。
(2)第54条(配当の禁止)
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
医療法人はそもそも「営利を目的とはしていない」という意味で、この規定が設けられています。
「医療法人に貯まった資金を無税で理事長に渡すこと」は、剰余金の配当と同じようなものと考えられ、生命保険の契約そのものがグレーなものとなります。
【税務上も役員賞与として課税対象になる事例がある】
このような生命保険の契約をしたことで、後日の医療法人の税務調査において、生命保険契約を譲渡した時点で医療法人から理事長に対して役員賞与が支払われたとして指摘された事例があります。
医療法人で役員賞与と指摘されますと、次のような影響があります。
(1)役員賞与は医療法人の損金には落とせませんので、法人税の課税対象になります。
(2)役員賞与について医療法人は源泉徴収をしておらず、また理事長個人も所得税を払っていない。
(3)上記の法人税と所得税を払っていないことについて、延滞税や加算税などの対象になります。
このように、役員賞与と指摘されますとトリプルパンチを受けることになります。
【良識ある保険担当者かどうかを見極める】
良識ある保険担当者であれば、お客様に不利益になるようなことがあれば上記のような説明を必ずすると思います。
メリットである「節税」だけを強調することは、非常に危険であると思います。
医療法人の理事長には、いろんな業者が接触を持とうと近寄ってきます。
このような提案があったときは、顧問税理士さんにご相談されることをお勧めします。
【相続税対策参考ブログ】
・医療法人の相続税対策に限界を感じていませんか?
・医療法人が出資持分の相続税対策に悩む理由(2016/06/22)
・診療報酬改定による医療法人の売却と創業家の相続税対策(2016/03/22)
・医療法人の相続税対策と海外銀行の資金管理運用(2015/02/25)
・医療法人の相続税対策に納税猶予制度は意味がない(2014/11/10)
・医療法人売却後の相続税対策(2014/09/08)
・開業医がMS法人を設立することで所得税の節税効果はあるのか?(2012/06/30)
・医療法人の相続税対策、生命保険は意味がない(2012/06/26)
・医療法人の相続税対策は節税本レベル知識では対応できない(2011/11/08)
・医療法人の相続税対策(2011/10/28)