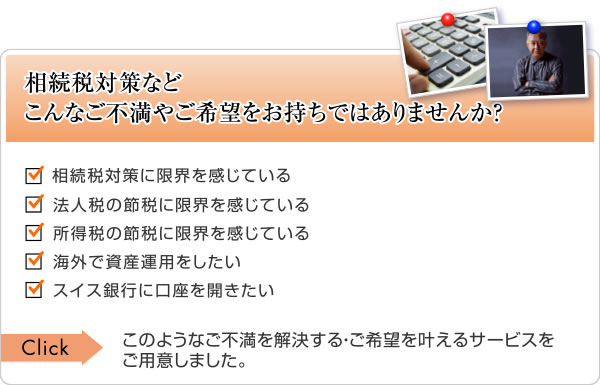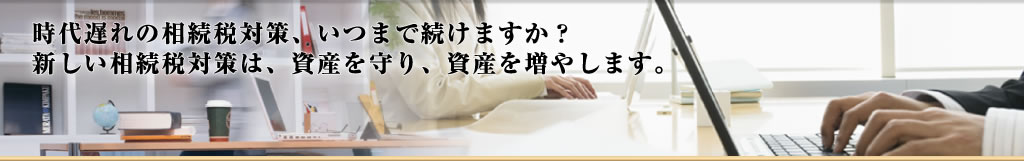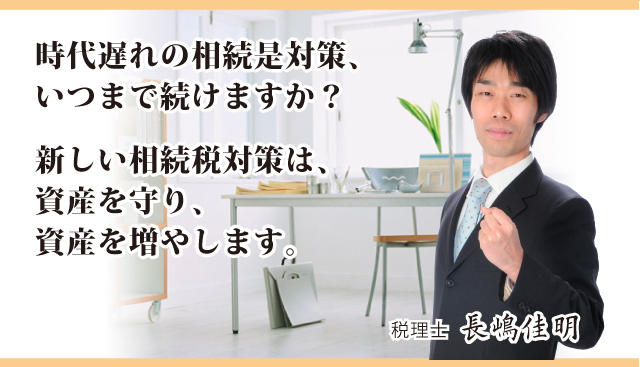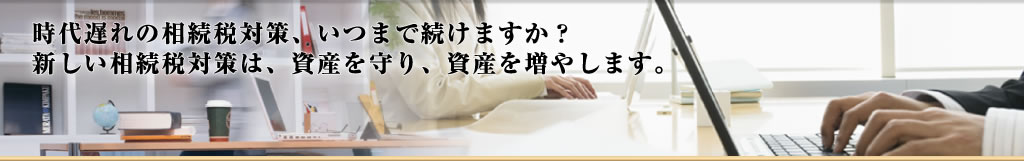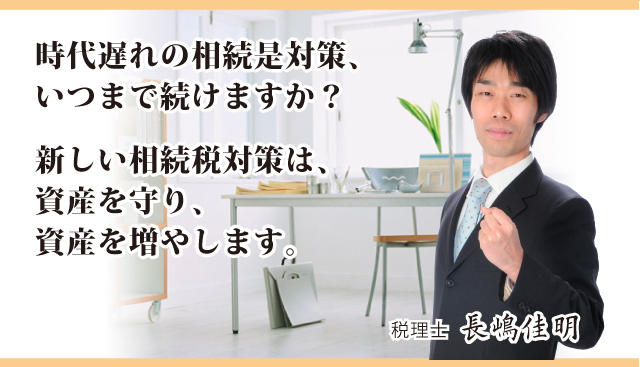このほど国税庁より、平成26事務年度(平成26年7月から平成27年6月までの間)に実施した所得税及び個人事業者の消費税について、税務調査の状況が公表されました。
平成26事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(国税庁)
国外財産調書を利用した税務調査が始まったこともあり、富裕層の海外資産への税務調査が強化されているようです。
この中で、相続税対策や所得税の節税にご興味がある方に関係する部分を抜粋してご紹介します。(参考:週刊税務通信、平成27年11月9日)
【富裕層への税務調査】
(1)いわゆる「富裕層」への対応
○国税庁では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などの、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に実地調査を実施しており、平成27事務年度においても積極的に取り組んでいきます。
○平成26事務年度においては、4,361件(前年比104.4%)の実地調査を実施し、追徴税額は総額で101億円となっています。
○また、1件当たりの追徴税額は231万円で、実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの追徴税額141万円の約1.6倍となっています。
(2)海外取引を行っている者の調査状況
○経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成27事務年度においても積極的に調査等を実施します。
○平成26事務年度における海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の件数は、3,322件(平成25事務年度2,717件)となっています。
○1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,944万円(平成25事務年度1,698万円)で、実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの申告漏れ所得金額877万円(平成25事務年度810万円)の約2.2倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は646億円(平成25事務年度461億円)に上ります。
(3)金地金等に係る譲渡所得の調査状況
○金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
○これに対し、国税庁では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成27事務年度においても積極的に調査等を実施します。
(注)「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。
○平成26事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は2,627件(平成25事務年度3,193件)、申告漏れ所得金額は117億円(平成25事務年度160億円)、非違1件当たりの申告漏れ所得金額は447万円(平成25事務年度502万円)となっています。
【所得税の税務調査の事例】
(1)海外法人から受け取った役員報酬の申告漏れ、タックスヘイブン国での資産運用益の申告漏れ(大阪国税局)
日本法人の代表取締役Aは、日本法人から得た役員報酬と配当金について所得税の確定申告を行った。
税務署において資料を検討したところ、Aに外国でも所得があることが想定された。
税務調査の結果、AはタックスヘイブンであるB国とC国において法人を設立し、それぞれ代表取締役を務めていることを把握した。
AはB国法人から役員報酬を得ていたが、日本で申告をしていなかったために課税した。
また、C国法人において資産運用を行っていたため、タックスヘイブン税制を適用し、資産運用益に対して課税した。
申告漏れ所得金額約6100万円、追徴税額約2600万円。
(2)海外での資産運用益の申告漏れ、国外財産調書の未提出(金沢国税局)
税務調査の対象となったA及びその配偶者Bについて、自動的情報交換資料等により、海外で資産運用を行っていることが見込まれたが、その運用益の一部が申告されていないことが想定された。
税務調査の結果、A及びBは海外にあるC銀行及びD銀行に口座開設していた。
預金の利子については申告していたものの、債券の利子については申告していなかったために課税した。
A及びBは国外財産調書を提出していたが債券の記載がなかったため、債券の利子に対する加算税について5%相当額を加算することとした。
さらに、Aの子供であるE・Fについても同様に海外で資産運用を行っていることを把握した。
子供Eについては、海外にあるC銀行及びD銀行における預金の利子・債券の利子・年金保険の収入を一切申告していなかった。
子供Fについては、海外にあるD銀行における預金の利子・債券の利子が申告漏れとなっていたために課税した。
子供E・Fは国外財産調書を提出していなかったため、子供Eの加算税に対して5%相当額を加算することとした。
子供Fについては重加算税を賦課し、配偶者Bから海外での資産運用資金の贈与を受けていたため、贈与税も課税した。
なお、子供E・Fから国外財産調書の提出を受けることとした。
申告漏れ所得金額約2600万円、追徴税額約400万円。
(3)金地金の譲渡所得のつまみ申告(東京国税局)
会社員Aは平成24年に金地金の譲渡を行ったことから所得税の確定申告を行った。
税務署において資料を検討したところ、申告された金地金以外にも貴金属を譲渡していることが想定された。
税務調査の結果、Aは平成24年において申告した金地金以外にも貴金属の譲渡を行っていたことを把握した。
また、平成23年以前においても金地金などの貴金属の譲渡を行っていたが申告していなかったことを把握した。
Aは「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出対象となる200万円超の金地金の譲渡のみを申告していた。
申告漏れ所得金額約5200万円、追徴税額約900万円。
(4)海外不動産の譲渡所得の申告漏れ(名古屋国税局)
銀行から提出された国外送金等調書から、税務調査の対象となったAは多額の海外送金を行っていた。
税務調査の結果、Aは送金した資金により海外不動産を購入しており、その後海外法人に海外不動産を現物出資していることが判明した。
海外不動産の現物出資により取得した海外法人の株式の時価が海外不動産の取得価額を上回っており、海外不動産の譲渡所得が申告漏れとなっていた。
なおAは、国外財産調書の提出をしていなかったが、取得した海外法人の株式の時価が12月31日時点において5000万円を超えていたことから、国外財産調書の提出を行うように指導した。
申告漏れ所得金額約2700万円、追徴税額約900万円。
【なぜ幼稚で危険な橋を渡ろうとするのか?】
海外法人を設立して日本の税金を逃れる、あるいは海外での資産運用による利益を日本で申告しない。
このような節税(脱税)手法はとても「古典的」であることは周知の事実です。
国税が調べればわかることなのですが、なぜ日本人はこのような幼稚な節税(脱税)をしてしまうのでしょうか。
それなりの地位におられる方がこのようなことをされますと、新聞などに名前が出てしまいますので、ご自身のお名前に傷をつけることになるのは明白です。
なぜこのような幼稚で危険な橋を渡ろうとするのでしょうか。
インターネットや週刊誌などに掲載されているタダ同然の情報を頼りにしているような方がいるとすれば、お止めになったほうが賢明です。
ご自身のためにもケガをしてからでは遅すぎます。
【相続税対策参考ブログ】
・相続税税務調査対策ガイド
・海外資産の税務調査は税務署を本気にさせる(2015/03/22)
・海外資産の税務調査はより一層の強化へ(2014/11/05)
・大金持ちの税逃れ、許さない 国税局が専門チーム設置(2014/07/14)
・富裕層・海外資産に対する所得税の税務調査が活発化(2013/11/08)
・所得税の税務調査、富裕層・海外取引を強化(2012/11/10)
・高額所得者の所得税の税務調査、海外取引を強化(2011/11/23)