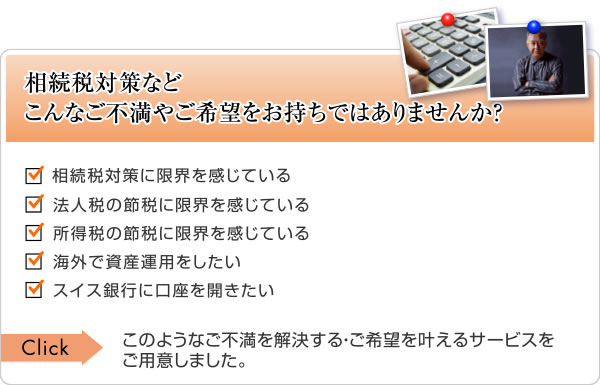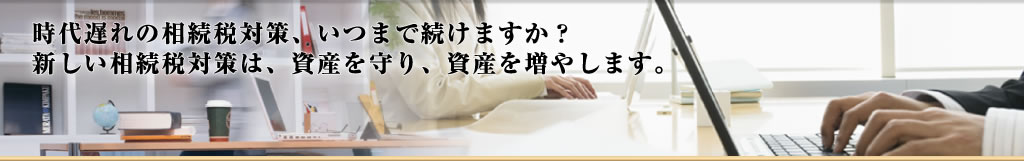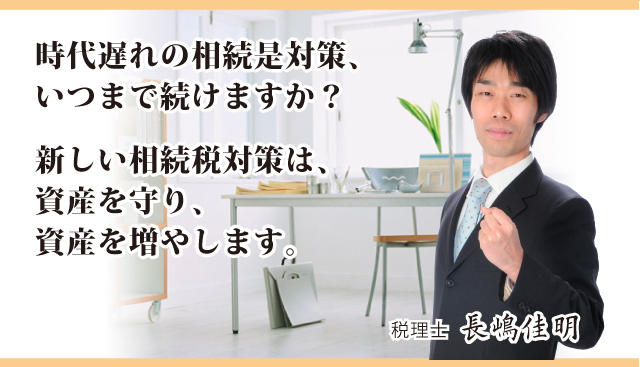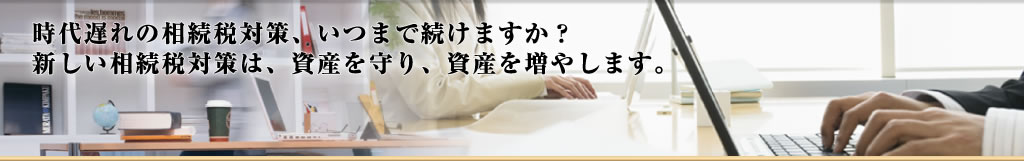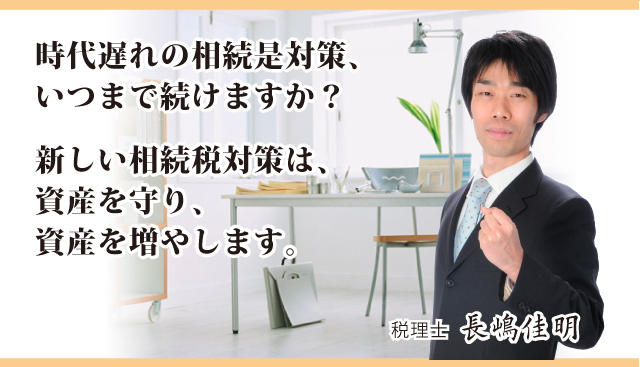先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしました。
お話を伺うと、お客様は次のことでお困りになっておられました。
『銀行の勧めで相続税対策を行ったものの、相続税を払うことができない。』
【銀行に勧められるままに相続税対策を行った】
お客様からさらに詳しいお話を伺うと次のような事情でした。
(1)相続税対策のため銀行に相談した。
(2)相続税対策のため借金をした賃貸アパートの建築や生命保険の加入を勧められた。
(3)銀行の提案する相続税対策を実行した。
(4)相続税対策の実行により、見込まれる相続税は節税になった。
(5)ところが、相続税対策のために手持ちの現金で不動産などを購入したため手持ち現金が少なくなりすぎ、日常生活に不安を感じている。
(6)確かに相続税の節税にはなったが、相続税を現金で払うことは不可能である。銀行の勧めで購入した不動産はいずれ売却することになるだろう。
お客様が不安に感じられていることは次の2点です。
(1)相続税対策をしたのに相続税を払えない
(2)手持ちの現金が大幅に減少したため、日常生活そのものが心配
相続税対策を行う目的として、相続税の節税があります。
相続税の節税ができたところで、その結果として「相続税を払えない状況であるならばその相続税対策は失敗である」と言えるでしょう。
さらに、お客様には「心理的不安」という日常生活にも影響が出ています。
過剰な相続税対策であったことは明らかだと思います。
なぜ、このような結果になってしまったのでしょうか。
それは、日本の相続税対策に根本的な問題点があるからです。
【日本の相続税対策の根本的な問題点】
日本の相続税対策の歴史を紐解くと、根本的な問題点が浮き彫りになります。
それは、日本の相続税対策が金融機関主導で行われてきた歴史的事実があります。
バブル時代には、次のような相続税対策が流行しました。
・借金をして賃貸アパートを建築
・借金をして生命保険に加入
銀行・不動産会社・生命保険会社がこぞって相続税対策の提案を行いました。
この状況は、30年後の現在でもなお何も変わりません。
一方、海外に目を向けると日本とはまったく異なる状況が見えてきます。
アメリカなど富裕層の歴史がある国々では、政府が国民のために相続税対策のための法整備をしています。
日本の相続税法のように、土地の評価額は公示価格の80%とするなど「時価と相続税評価額に差をつける」といった低レベルなお話ではなく、相続税について根本的に解決することができるような法整備を行っています。
このように、日本と富裕層の歴史がある海外の国々との間には、相続税対策を誰が主導しているのかが根本的に異なります。
・日本=金融機関など(民)
・富裕層の歴史がある海外の国々=政府(官)
日本の相続税対策は「民」の主導で行われていますので、彼らは税法の抜け道となるような売れる商品を開発し販売します。
そのため「官」主導ではない日本の相続税対策は常に「税制改正リスク」を抱えており、現実に税法が改正され節税方法が封じられていることはみなさまもご存じの通りです。
このような背景から、いつしか相続税対策といえば「節税」ではなく「争族対策」や「納税資金の対策」といった概念に変化を遂げていき現在に至ります。
いうなれば「相続税の節税をすることができない」と銀行や税理士自身が認めたものと同じであると考えます。
「バブル時代に流行した相続税対策は時代遅れであり、相続税対策の考え方を根本的に変える必要がある」と税理士長嶋は考えます。
【相続税対策参考ブログ】
・トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税(2014/12/24)
・相続税対策にもファーストクラスとエコノミークラスがある(2013/08/20)
・相続税対策に「何もしない」という結論もある(2013/07/10)
・相続税対策の税制改正リスク(2013/06/01)