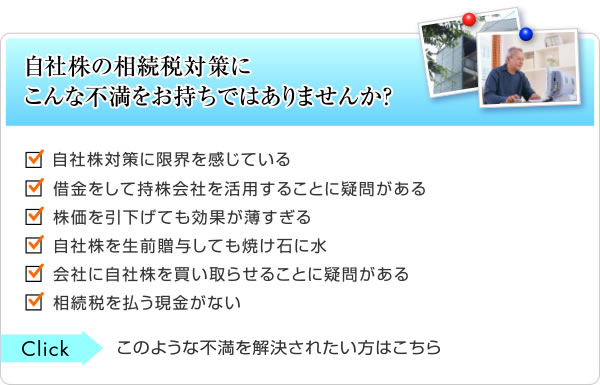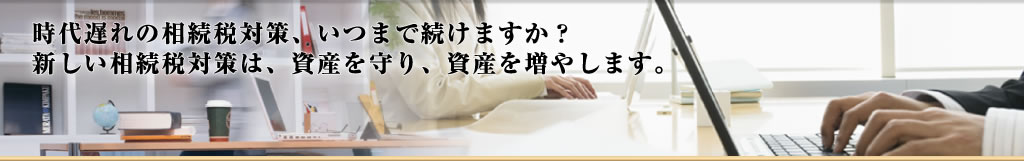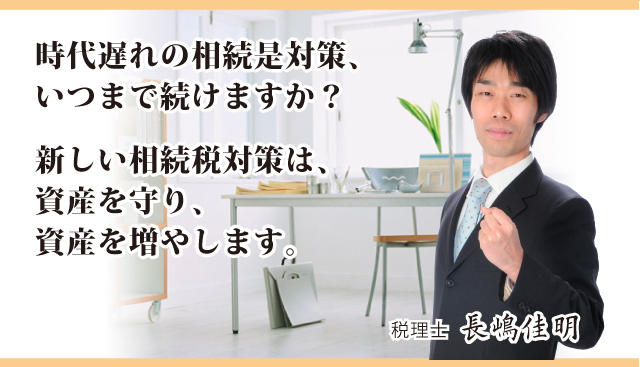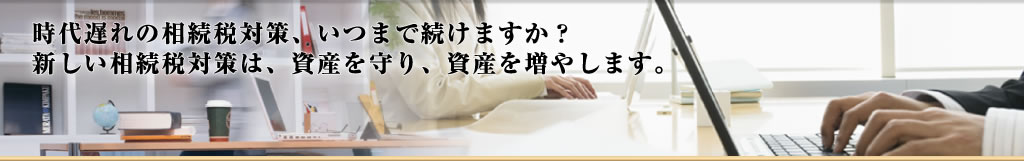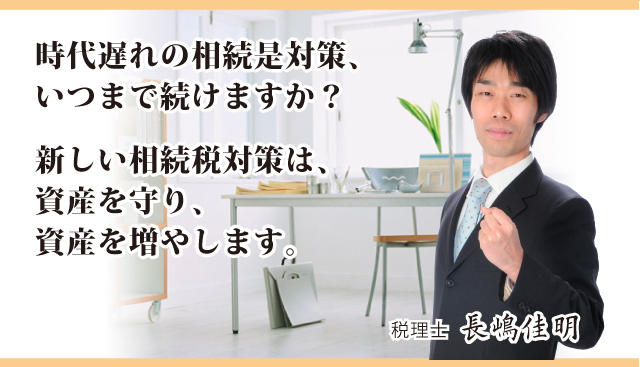先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様は会社経営をされており、自社株の相続税対策が必要とのことでした。
また、会社の事業拡大のために海外展開をさらに進めていく計画をされていましたが、以前からある課題をクリアできずに困っているとのことでした。
お客様の会社は上場も視野に入れていることから監査法人を顧問に付けているそうですが、自社株の相続税対策と事業の海外展開について以前から監査法人に相談しているものの、お客様が納得できるような提案が出てこないそうです。
そこで、自社株の相続税対策と海外での事業展開の両方の相談ができる会計士・税理士を探されていたときに、税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。
【自社株の相続税対策は慎重に、会社の事業拡大のため海外展開を加速】
お客様が私どもに連絡をくださった理由を伺うと、次のようなお話でした。
(自社株の相続税対策)
・自社株の株価が非常に高額になっているため将来の相続税が不安である
・自社株についての相続税対策が必要と感じている
・自社株の株価があまりにも高額になり過ぎているため、動くに動けない状況である
・金額が大きすぎるため、自社株対策は慎重に検討していきたい
(海外での事業展開の拡大)
・会社の事業拡大のため、以前から海外展開をしている
・国内市場は飽和状態であることから、海外展開をさらに加速していきたい
・以前から海外で事業展開をしているが、事業がうまく回る仕組みを構築できていない
・まずは、事業の海外展開について相談したい
自社株の株価は相当高額になっており、一旦動き出せば止められない状況でしたので、自社株の相続税対策には慎重な対応が必要でした。
また、会社の事業拡大について海外展開を加速していくことのほうが緊急性を要するようでしたので、まずは海外での事業展開について詳しくお話を伺うことにしました。
【海外での資金調達コスト(借入金利)が高すぎる】
お客様の会社は以前から海外で事業展開をされています。
従来から展開している事業に加えて、これに関連する新事業の立ち上げをいくつか計画されており、実際にそのいくつかは既に事業として動いているとのことでした。
お客様の会社は海外進出当初から「ある課題」をクリアすることができず、大きな悩みの種だったそうです。
ある課題とは、次のようなことでした。
・日本国内・日本国外を問わず、事業にキャッシュが回らないと会社は死んでしまう
・事業を拡大するには自己資金だけでは不足するため、現地の銀行から資金調達をしている
・現地の銀行から資金調達しようとすると、借入金利は年10%を超えてくる
・単純に、事業単体の営業利益率が10%以上でないと利益が出ない
・営業利益率10%以上を確保できる事業しか展開できないが、順調に利益が出ている
・海外の運転資金を日本の本社が調達するにしても、日本国内の事業でも資金が必要なため送金できる金額は限られてくる
・現地の銀行から資金調達する際の金利が高すぎることが以前からの課題
・資金調達コスト(借入金利)を引下げることができればより多くの利益を出せ、また事業が減速した際にも損失を抑えることができる
資金調達コスト(借入金利)が年利10%を超えてくる。
つまり、先進国ではなく新興国での事業展開であることは容易に想像できます。
【監査法人の仕事は監査をすることであってコンサルをすることではない】
海外で事業展開を進めていく際には、多くの場合次のようなことが課題として挙がってきます。
・資金調達はどのようにして行うのか
・資金調達コストをどのようにして抑えるのか
・どのようにすれば海外事業にうまくキャッシュが回るのか
日本であろうと海外であろうと、キャッシュが回らなければ事業が死んでしまいますので、これらは最重要課題とも言えます。
これらの課題を解決できない会社は、日本の本社から運転資金をわざわざ送金しているのが実情です。
これは、監査法人が顧問に付いているような大規模な会社でも例外ではありません。
そもそも、監査法人はこれらの課題を解決することができません。
その理由は、彼らの仕事は監査をすることであって、コンサルをすることが仕事ではないからです。
これは、監査法人が自社株の相続税対策について、誰もが知っているありきたりの提案しかできないことにも同じことが言えます。
また、彼らは海外のことを知らないため、なおさら海外の課題に対応することができません。
その証拠に、私どもにご相談いただくお客様の会社の顧問がビッグ4(E&Y、Deloitte、KPMG、PWC)であることが少なくありません。
【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策と海外事業展開に国際税務のうんちくは不要(2014/05/07)
・相続税対策を監査法人に相談したが解決できない(2013/04/26)
・アベノミクス失敗に備えるための相続税対策や資産保全(2013/04/08)
・相続税対策で法人税と所得税を節税する方法(2012/02/10)