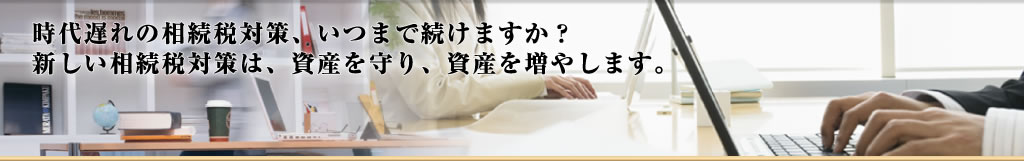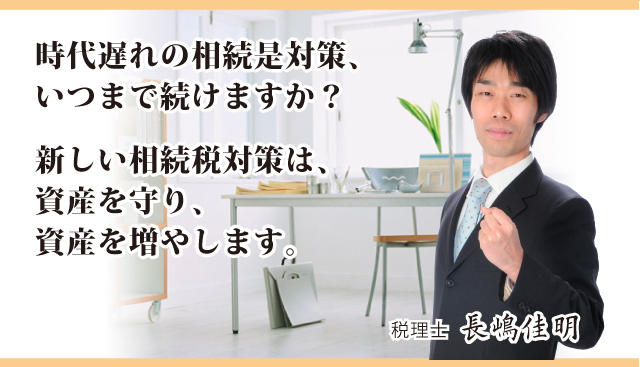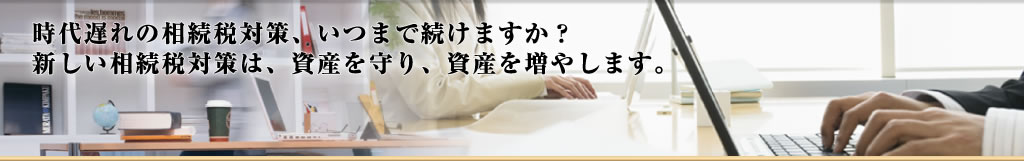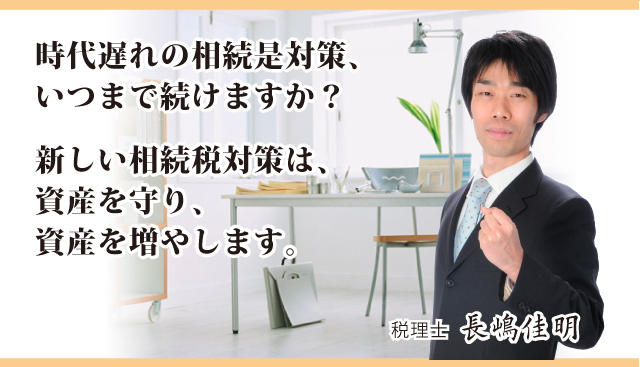平成23年12月10日、政府税制調査会及び臨時閣議で「平成24年度税制改正」が決定されました。
その中で、特に相続税対策が必要なお客様に関係する項目だけを取り上げたいと思います。
【海外法人に利息を支払う節税に制限】
海外法人に利息を支払うことで、日本国内の法人は経費とすることができます。
この海外法人がグループ会社である場合、日本国内の法人の節税につながります。
そのため、海外法人に支払う利息に経費として認めることに制限がされることになりました。
(平成24年度税制改正大綱より)
『支払利子を利用した課税ベースの流出リスクに対する近年の主要先進国における対応を踏まえ、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するための措置を導入することとします。』
【税制は改正されることが大前提】
税理士長嶋にご相談くださる方は、相続税対策として海外法人を利用される方だけではなく、海外でビジネスを拡大させるために海外法人を利用される方もおられます。
税理士長嶋がいつもお話させていただくことは次の事です。
『税制が改正されたからといって右往左往しなければならないような節税対策は、最初からしないほうがいい』
税理士長嶋は何を言いたいのかと申しますと、税制は改正されるものであることを理解して受け入れなければならないということです。
税制が改正されれば節税効果がなくなるような節税対策は、根本的な解決にはなりません。
ましてや、相続税対策は長期にわたり対策を行うことも珍しくはないので、現在の相続税法では節税になっているかもしれませんが将来の20年後の相続税法でも節税になっているのかどうかは誰にもわかりません。
つまり、税制が改正されたとしても何ら影響を受けない根本的に解決できる方法を検討する必要があると考えます。
では、本当にそのような方法があるのか?
みなさまの顧問税理士さんに質問してみてください。
答えは一つ「そんな方法はない」という回答だけだと思います。
【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策に海外法人の活用でトラブル多発(2012/01/04)
・国際税務に強い税理士は海外を使った相続税対策を知らない(2011/11/22)
・相続税などの節税対策に海外法人設立は効果があるのか?(2011/09/05)
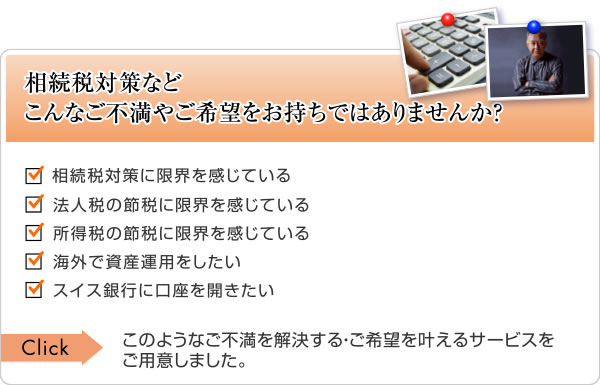
【海外法人に利息を支払う節税についての税制改正の内容】
海外法人に利息を支払い節税をされている日本法人は、経費である支払利息に制限されることになりますが、その具体的な内容について税制改正大綱では次のように述べられています。
(3)関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)
〔国税〕
所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、次の措置を講じます。
① 概要
法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとします。
② 関連者の範囲
関連者の範囲は、その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等とします。
③ 関連者に対する純支払利子等の額
関連者に対する純支払利子等(以下「関連者純支払利子等」といいます。)の額は、関連者に対する支払利子等(以下「関連者支払利子等」といいます。)の額の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
イ 関連者支払利子等
(イ) 支払利子等の範囲は、利子、利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます。)及び関連者保証による借入れに伴う保証料等とします。
(ロ) 関連者支払利子等には、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る支払利子等は、含まれないものとします。
(ハ) 関連者支払利子等には、その関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
ロ 関連者支払利子等の額の合計額に対応する受取利子等
(イ) 受取利子等の範囲は、利子及び利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます。)とします。
(ロ) 関連者純支払利子等の額の計算において関連者支払利子等の額の合計額に対応するものとして控除される受取利子等の額は、総受取利子等の額から上記イ(ロ)の債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を控除した残額のうち関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額(上記イ(ロ)の債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を除きます。)に占める割合に応じた金額とします。
(ハ) その法人が関連者である居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは外国法人から受ける利子等(以下「国内関連者受取利子等」といいます。)の額は、原則として上記(ロ)の総受取利子等の額に含まれないものとします。ただし、これらの関連者が非関連者又は国内に恒久的施設を有しない非居住者若しくは外国法人から利子等の支払を受ける場合には、その金額は、国内関連者受取利子等の額を限度として、上記(ロ)の総受取利子等の額に含まれるものとします。
④ 調整所得金額
調整所得金額は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額とします。
⑤ 繰越損金不算入額
当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」といいます。)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するものとします。
⑥ 適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
イ その事業年度における関連者純支払利子等の額が1千万円以下であること
ロ その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%以下であること
なお、上記ロの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
⑦ 連結納税における本制度の適用
連結納税における本制度は、以下のとおり、連結グループを一体として適用するものとします。
イ 損金不算入額
(イ) 各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額からこれに対応する受取利子等(グループ内の他の連結法人からの受取利子等を除きます。)の額の合計額を控除した残額が、連結調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は当期の損金の額に算入しないものとします。
(ロ) 連結調整所得金額の計算における調整は、原則として単体納税の場合と同様とします。ただし、グループ内の他の連結法人からの受取配当等に係る益金不算入額等については加算の対象としない等の調整を行うものとします。
ロ 適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
(イ) その連結事業年度における各連結法人の関連者純支払利子等の額の合計額が1千万円以下であること
(ロ) その連結事業年度における各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額が各連結法人の総支払利子等の額の合計額の50%以下であること
なお、上記(ロ)の総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
⑧ 他の制度との関係
イ 本制度と過少資本税制との適用関係
本制度と過少資本税制の双方が適用となる場合には、その計算された損金不算入額のうちいずれか多い金額を当期の損金不算入額とします。
ロ 本制度と外国子会社合算税制との適用関係
内国法人が関連者である外国子会社等に対して支払った利子等につき外国子会社合算税制と本制度の双方が適用となる場合には、本制度による損金不算入額(その外国子会社等に対する支払利子等に係る部分に限ります。)から外国子会社合算税制による合算所得(その外国子会社等に係るものに限ります。)に相当する金額を控除する等の調整を行うものとします。
⑨ その他
イ 適格合併又は100%子会社の解散による残余財産の全部分配が行われた場合において、被合併法人又はその子会社が繰越損金不算入額を有するときは、その繰越損金不算入額を合併法人又は親会社に引き継ぐものとします。
ロ その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。