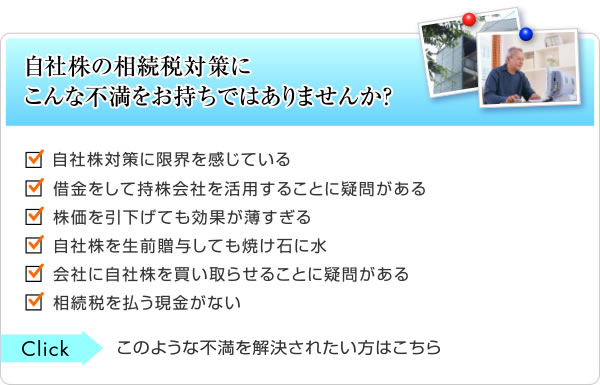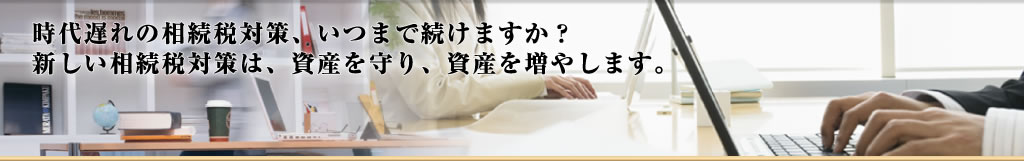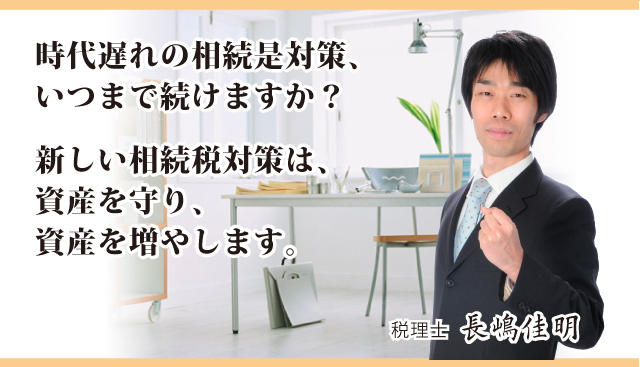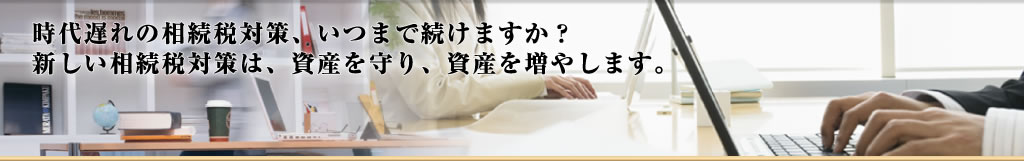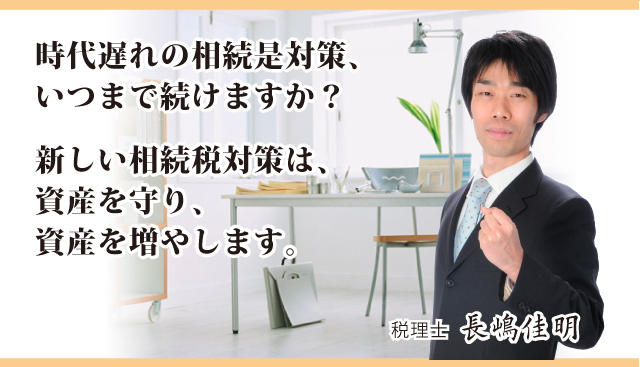先日、相続税対策のお手伝いをさせていただいているお客様から、次のようなご相談がありました。
『信託を活用した相続税対策を外資系の金融機関から提案されているが、本当に相続税対策になるのでしょうか?』
【信託を活用した相続税対策とは?】
信託を活用した相続税対策は、その昔、平成9年ごろに流行しました。
その後、相続税の節税効果を封じ込めるため、平成11年と平成12年に通達の改正が行われた歴史的な経緯があります。
具体的には、財産を信託し信託された財産を収益受益権と元本受益権に分離をすることで、相続税の対策が可能でした。
例えば、次の条件の場合、次のような相続税対策の効果がありました。
(1)委託者:会社経営者(Aさん)
(2)受益者:収益受益権→会社経営者(Aさん)
元本受益権→会社の後継者である長男(Bさん)
(3)信託財産:Aさんが経営する自社の株式、1億円相当
(4)信託の期間:20年
(5)信託からの配当:自社の株式の配当金、年500万円
・収益受益権の評価額=8584万円(年500万円×17.169(基準利率1.5%の複利年金原価率))
・元本受益権の評価額=1416万円(1億円-8584万円)
現在の価値で1億円の自社株を信託にすることで、1416万円まで価値が下がります。
信託を活用し評価額を圧縮することで、会社後継者であるBさんに贈与をすれば相続財産を減らすことができました。
【信託法の改正により、節税に対する規制を強化】
平成19年9月に施行された新しい信託法では、信託を利用する際の課税関係について租税回避を防止することに重点が置かれたため、基本的には租税回避ができないようになっています。
信託を利用して相続税対策を行うことを考えるのは諦めたほうが良いでしょう。
その他、
・金利の状況により、評価額が変わる
・金利の状況が変わることで、元本の評価額が変わる
・税制改正
などのリスクがありますので、当初見込まれた節税効果を失う可能性もありますので、注意をする必要があります。
【相続税対策参考ブログ】
・アメリカの信託は日本の相続税対策も考慮すべき(2014/03/22)
・国外財産調書制度の対策にニュージーランド家族信託は意味がない(2013/05/03)
・相続税対策に効果がないニュージーランドの家族信託(2013/04/30)