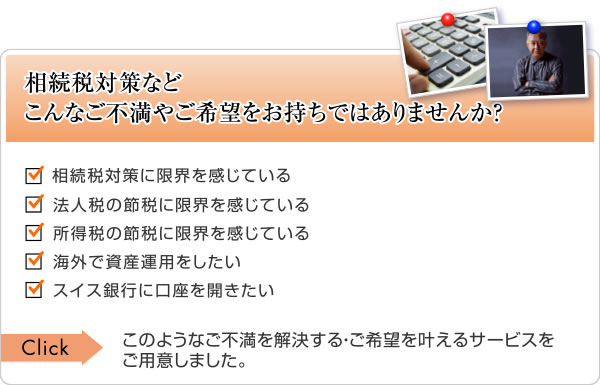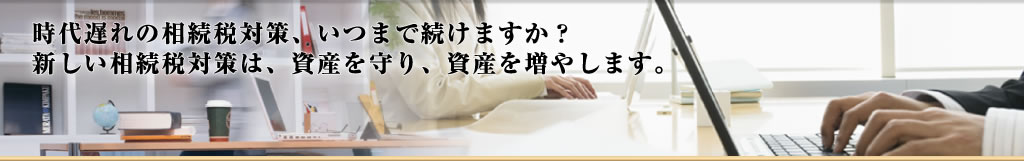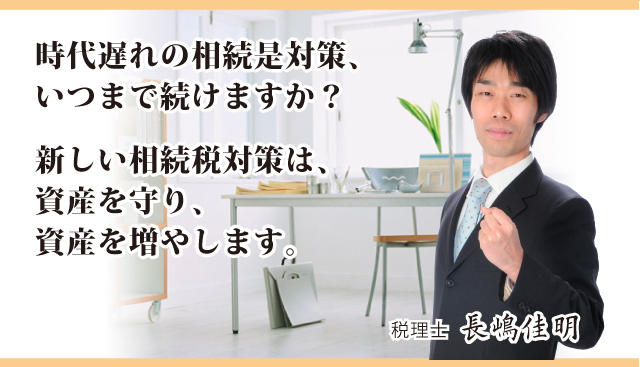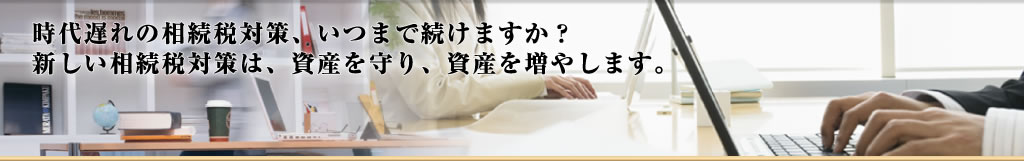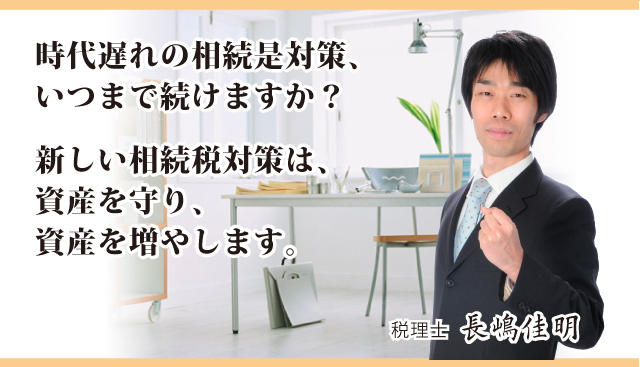相続税対策を考える場合、生命保険はよく活用されるものです。
相続税対策において、生命保険がよく活用される理由は、次の3つに効果があるためです。
(1)相続税を払うための資金を作ることができる
(2)相続税において生命保険には非課税があるため相続税の節税になる
(3)遺産相続をするときに争うことを防ぐ効果がある
【生命保険金は相続財産ではありません】
(原則)
被相続人の死亡により支払われる生命保険金は相続財産ではありませんので、生命保険金は遺産相続の対象にはなりません。
この生命保険金は、保険金受取人となっている相続人自身の財産となります。
保険金受取人となっている相続人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
(例外)
特段の事情がある場合には、相続財産に含まれます。
この場合、生命保険金は遺産相続の対象にはなります。
※最高裁判決(最決平成16・10・29 民集58巻7号1979頁)
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる。
【遺産相続をするときに争うことを防ぐ効果がある】
生命保険金が遺産相続をするときに争うことを防ぐ効果がある理由は、次の2点です。
(1)財産分けをする必要がない
(2)葬儀費用などの支払いに充てることができる
(1)財産分けをする必要がない
被相続人が財産を預金として持っていた場合、その預金は基本的には相続人の間で話し合われ、遺産分割を行うことになります。
しかし、被相続人の死亡により支払われる生命保険金は、保険金受取人となっている相続人自身の財産となりますので、遺産分割の手続きは必要ありません。
(2)葬儀費用などの支払いに充てることができる
被相続人が財産を預金として持っていた場合、その預金は基本的には相続人の間で話し合われ、遺産分割を行うことになります。
財産分けの話し合いまとまるまでは、銀行から預金を引き出すことができません。
そのため、葬儀費用の支払いや病院への入院費用の支払いなど、相続直後に必要な資金が準備できない可能性があります。
しかし、被相続人の死亡により支払われる生命保険金は、保険会社に書類を提出すれば早ければ1週間ほどで生命保険金が相続人の銀行口座に振り込まれてきますので、現金を準備することができます。
【生命保険金が相続財産ではない理由】
生命保険金は、生命保険会社と契約者との間で「被保険者が亡くなったら保険金受取人に保険金を支払ってください」という「契約」により支払われるものです。
この契約は、保険金受取人が生命保険会社へ死亡保険金を請求する権利を持っているのであり、被相続人が死亡保険金を請求する権利を持っているのではありません。
死亡保険金を請求する権利を持つのは保険金受取人であるため、死亡保険金が相続人自身の財産となります。
【生命保険金に相続税が課税される理由】
生命保険金は相続財産ではありません。
このように言われると、少しでも相続税を節税したいと思う方は次のように考えるのではないでしょうか。
・預貯金として持っていれば相続財産として相続税が課税される。
・預貯金ではなく生命保険であれば相続税が課税されない。
・持っている預貯金を引き出して生命保険に加入すれば、相続税の節税になる!
このようなことを防ぐため「生命保険金は相続財産ではないですが、相続税を計算するときには例外的に相続財産に含めることにしましょう」という意味で「みなし相続財産」と呼ばれています。
【相続税対策関連ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険
・相続税対策に生命保険の非課税を利用する(2011/04/12)
・相続税対策に生命保険を利用して納税資金を確保する(2011/04/11)