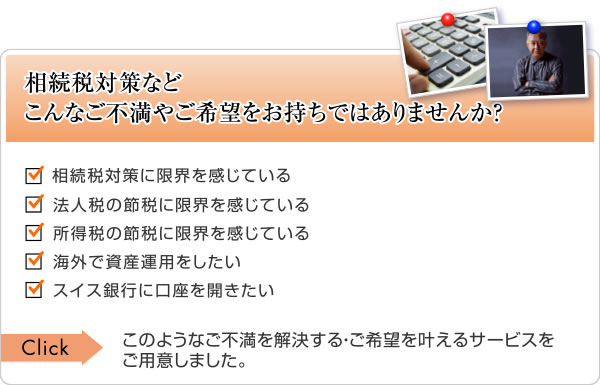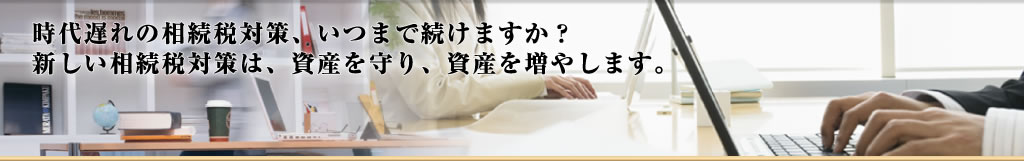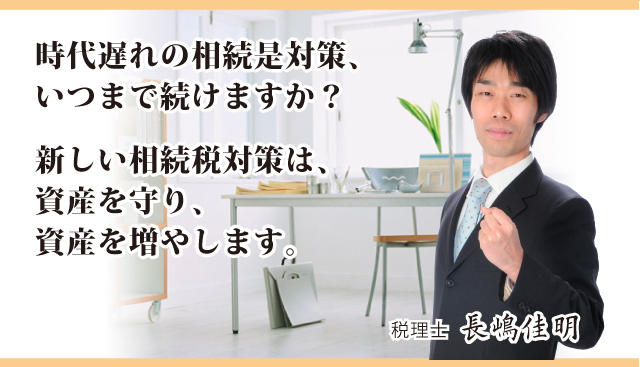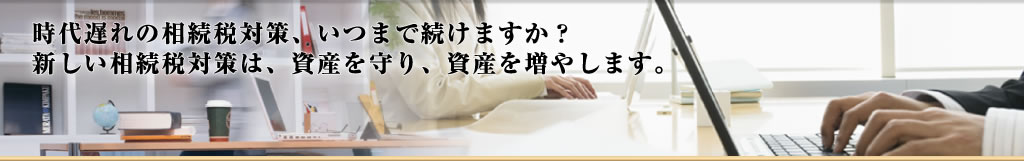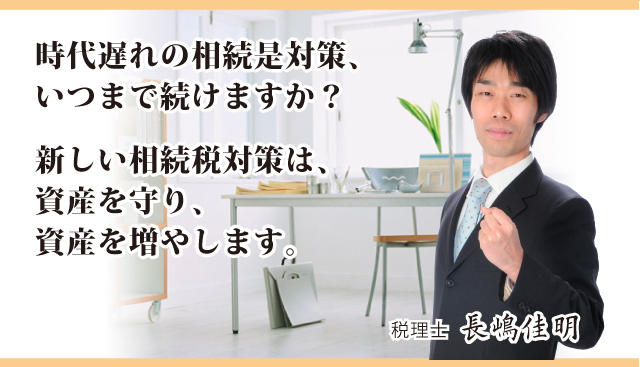財務省は政府税制調査会において、相続税の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」について、いわゆる「家なき子特例(特定居住用宅地等)」と「貸付事業用宅地等」の適用条件を厳格化する見直し案を示し、平成30年度税制改正大綱に盛り込む見通しです。
小規模宅地等の特例について適用条件を厳格化する理由は、小規模宅地等の特例制度を悪用した節税策が横行しているためです。
今回改正が予定されている「家なき子特例(特定居住用宅地等)」は、週刊誌や新聞に掲載されるような有名な節税スキームでした。
なぜ日本の税理士は、法制度の政策目的や立法趣旨に反する行為を「節税」と呼び、顧客に節税スキームと称して提案し実行させるのでしょうか。
政策目的や立法趣旨に反する節税を国税は「制度を悪用した節税」と考え、節税スキームを使えなくするために税制改正が行われてきたことは、歴史的事実として誰もが知るところです。
なぜ日本の税理士は、過去の歴史や経験から学ぼうとはしないのでしょうか?
法制度の政策目的や立法趣旨に反する節税として「一般社団法人を利用した節税スキーム」が問題視され、同様に平成30年度税制改正において節税策が封じられる予定です。
このことについて、2017年12月6日の相続税対策ブログ「一般社団法人節税スキームの税制改正、銀行税理士の責任問題へ」にてご紹介しています。
税務の専門家である税理士の存在意義は、法制度の政策目的や立法趣旨・学説等から将来の税制を予測し、将来における税務上のリスクまでも適切に顧客に説明することだと税理士長嶋は考えます。
単に、今の税制だけに注目し、節税というメリットだけを意図的に強調することで顧客の関心を引き、税法に定める表面上の形式的な条件だけを満たすためだけの不自然な行動を顧客に勧めるのは、無資格者である銀行やコンサルタントと称する人たちが行うことです。
相続税専門と称する税理士の中には、相続税対策の基本は小規模宅地等の特例をいかに活用するか?と熱く語る人がいます。
いかに活用するか?という発想そのものが、法制度の政策目的や立法趣旨に反して意図的に小規模宅地等の特例を適用できる状況をいかに作り出すか?を考えることを意味します。
このような法制度の政策目的や立法趣旨を理解しようとしない税理士は、税務の専門家である税理士としての自覚が足りないだろう。
これは、無資格者である銀行やコンサルタントと称する人たちと手を組み、セールス目的で顧客に近づく税理士にも同じことが言えるだろう。
法制度の政策目的や立法趣旨を考えていては、節税をセールストークとして顧客の背中を押すことができなくなり、銀行のセールスにつなげられません。
【いわゆる「家なき子特例」を悪用した節税策】
相続税には、被相続人の自宅を配偶者や親族が相続した場合に、相続税の負担が重くならないように配慮する特例制度があり、小規模宅地等の特例制度と呼ばれています。
この特例制度には、転勤や賃貸住まいなど相続人の生活環境を考慮して、相続開始前3年以内に持ち家がない場合にも、相続税の負担を軽くすることになっています。
この軽減措置は、いわゆる「家なき子特例」と言われており、被相続人の自宅の土地の評価額を330平方メートルまで8割引にしてくれる制度です。
この「家なき子特例」を悪用した節税策が横行しているため、国税は問題視しています。
「家なき子特例」の条件として「相続開始前3年以内に持ち家を持たない人」というものがあり、この状況を意図的に作り出すことを世の中の税理士は「節税」と呼んでいました。
例えば、
・自宅を所有する人が、子どもに自宅を贈与や売却して持ち家を持たない人となり、そのまま子どもと一緒に生活する
・自宅を所有する人が、親族が設立した資産管理会社に自宅を贈与や売却して持ち家を持たない人となり、売却後は役員社宅としてそのまま住み続ける
・自宅を所有する人が、親族が設立した一般社団法人に自宅を贈与や売却して持ち家を持たない人となり、売却後は理事社宅としてそのまま住み続ける
この状態で3年以上生活し、親の相続が発生すれば「家なき子特例」が適用され、相続税の負担が軽くなるという節税方法です。
この節税方法は、新聞や雑誌で紹介されるほど有名なもので、週刊誌に取り上げられるような節税方法は、税制改正されて当たり前ですので何も驚きません。
そもそも「家なき子特例」は、居住用宅地等の相続税評価額を軽くすることで、相続人の生活基盤を確保することを目的とした制度です。
「家なき子特例」の適用を受けるために、わざわざ持ち家を手放し、親族や親族が設立した資産管理会社・一般社団法人に持ち家を移して、引き続きその持ち家で生活するような行為は立法趣旨に反します。
立法趣旨に反する節税を国税は「制度を悪用した節税」と考えますので、税制改正をして節税スキームに蓋をするのは当然です。
このような制度を悪用する節税スキームを封じるため、平成30年度税制改正大綱において、次のような改正が盛り込まれる予定です。
・3親等内の親族、関係する同族会社・一般社団法人などの所有する家屋に居住している者を「家なき子特例」の対象から除外
・被相続人が居住していた家屋を相続する者から、相続開始前にその家屋を所有していた者を除外
この改正は、平成30年4月1日以後に開始する相続について適用される見込みです。
【貸付事業用宅地等を悪用した節税策】
小規模宅地等の特例制度の中には、賃貸マンションや賃貸アパートなど被相続人が貸付事業をしていた土地についても、相続税の負担を軽くすることになっています。
貸付事業用宅地等については、土地の評価額を200平方メートルまで5割引される制度です。
この貸付事業用宅地等を悪用した節税策が横行しているため、国税は問題視しています。
相続税は、現金で財産を持っているよりも不動産で持っているほうが安くなることは、相続税を気にされる方であれば誰もが知っていることです。
これを利用すれば、被相続人の生前中に被相続人の現金を使って不動産を購入して、貸付事業用宅地等の適用を受ければ土地の評価額は200平方メートルまで5割引できます。
貸付用の不動産は居住用不動産や事業用不動産に比べて購入しやすく売却もしやすいため、一時的に相続税の負担を軽くする節税スキームとして国税は問題視しています。
この理屈を考えてみると、貸付用の不動産として国税がターゲットにしているのは、償却年数が過ぎた木造アパートではなく、近年節税手法として問題視されているタワーマンションであると感じます。
このような制度を悪用する節税スキームを封じるため、平成30年度税制改正大綱において、次のような改正が盛り込まれる予定です。
・相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産は、小規模宅地等の特例制度から除外
・ただし、事業的規模で貸付けを行っているものは除きます
この改正は、平成30年4月1日以後に開始する相続について適用される見込みですが、同日前に賃貸を開始した不動産は除くという経過措置が講じられています。
【会計検査院も別の角度から小規模宅地等の特例制度を問題視】
会計検査院が2017年11月29日に公表した「租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について」において、会計検査院として「小規模宅地等に関して事業または居住の継続への配慮という政策目的に沿ったものとはいえない」との指摘をしています。
会計検査院が問題視しているのは、小規模宅地等の特例を適用した後、短期間で不動産を売却している事例があり、財務省に対して今後十分な検証が必要と指摘しています。
来年度以降に税制改正される可能性が出てきましたので、今後の動きが注目されます。
相続の後、短期間で不動産を売却している事例として、会計検査院は次の事例を掲げています。
(会計検査院が指摘した事例)
・相続人Aは、平成26年分の相続税申告書等において、相続した土地249.70平方メートル、現金預金28,53 8,289円、家屋4,477,440円等を相続した。
・被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地198.4 6平方メートル(このうち相続人Aの持分は2分の1。以後、持分に係る価額のみ表示)について、事業を承継することとして、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用した。
・土地の相続税評価額51,599,600円から50%相当額である25,799,800円を減額し、3,075,100円(不動産貸付事業の土地に係る相続税額は1,537,631円)を相続税として納税した。
・相続人Aは、保有継続要件である相続税の申告期限の翌日(相続開始日26年3月29日の翌日から10か月を経過した日である27年1月30日)の約1か月半後である27年3月13日に不動産貸付事業の土地を64,500,000円で売却した。
・相続人Aは「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)」の規定を適用して、不動産貸付事業の土地に係る相続税額1,537,631円を取得費に加算して譲渡収入から控除するなどして、譲渡所得59,523,207円に対する譲渡所得税額8,928,450円を納税した。
・もし、相続人Aが小規模宅地等の特例等を適用しなかったとして会計検査院において試算したところ、相続税額は5,098,200円増加して8,173,300円となる。
・一方で、取得費に加算される相続税額が3,658,456円増加して5,196,087円となることから、譲渡所得税額は548,850円減少して8,379,600円となる。
・したがって、相続人Aの負担する納税額は、相続税と譲渡所得税額の差引きで 4,549,350円増加することとなる。